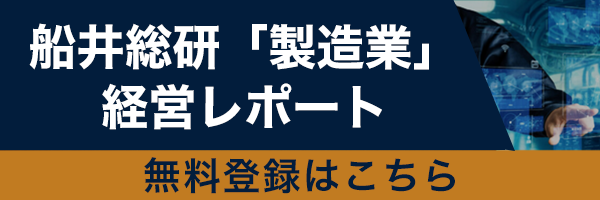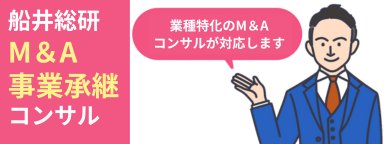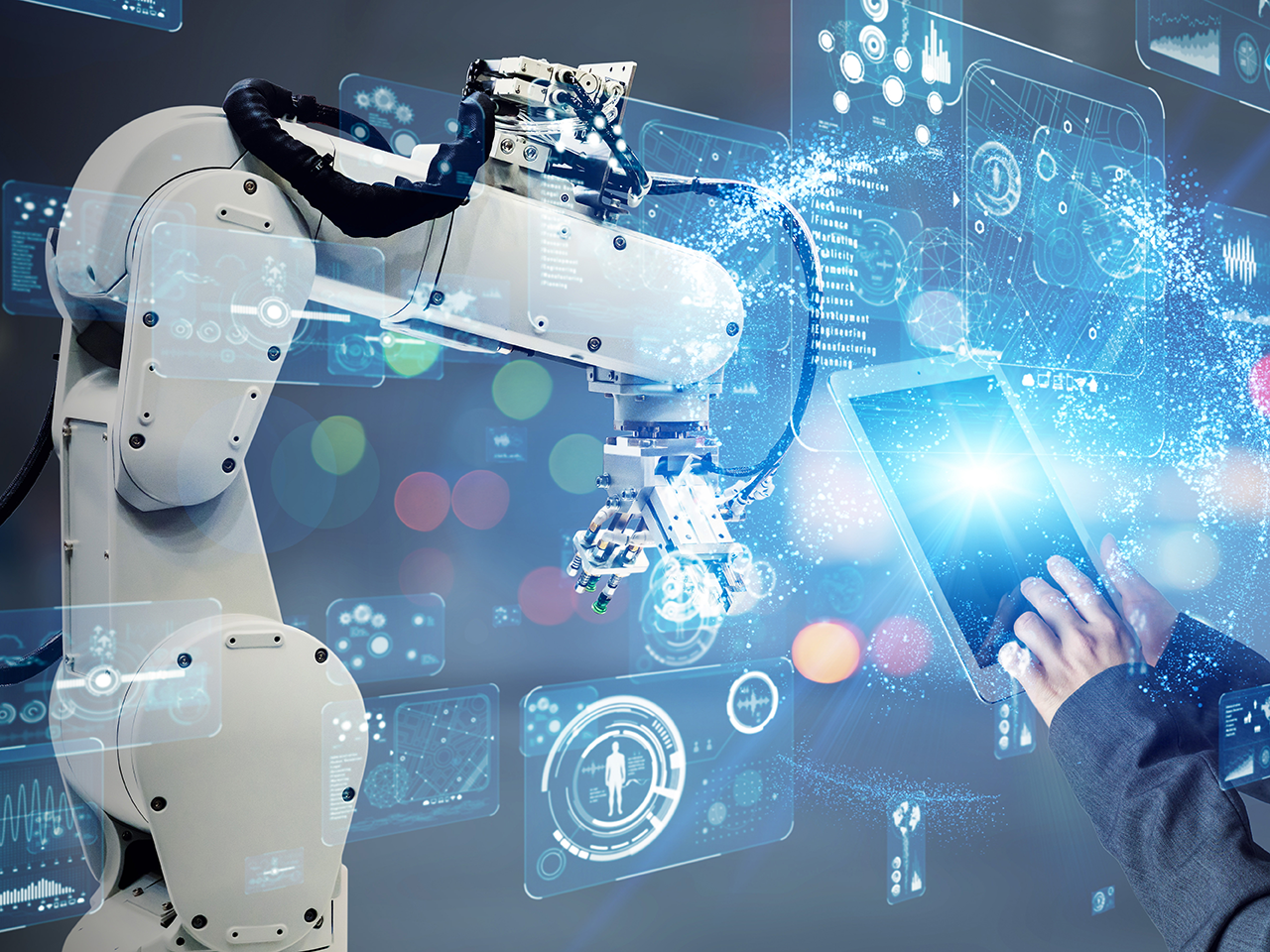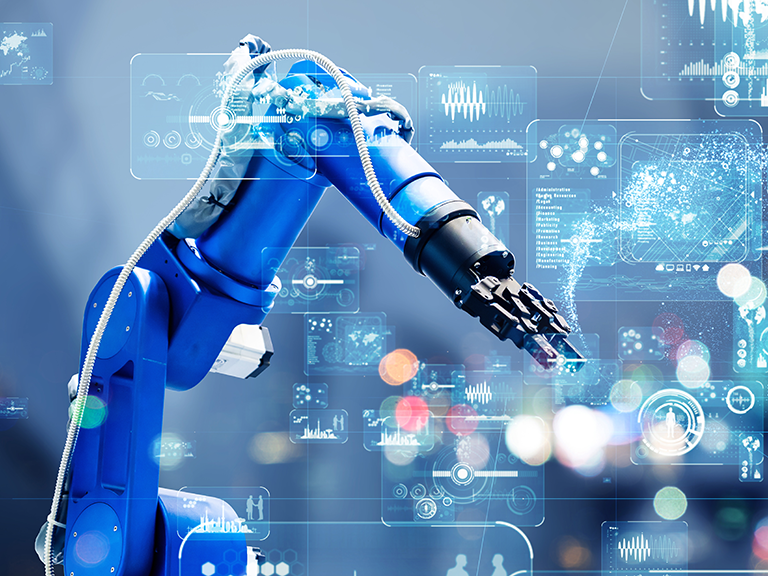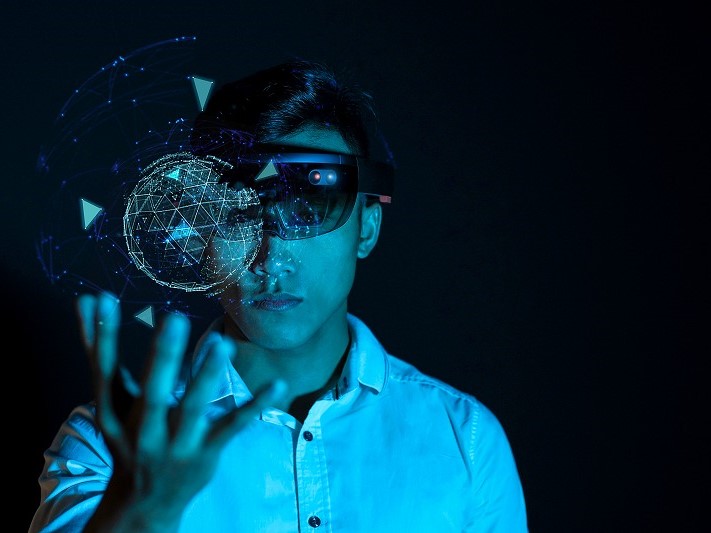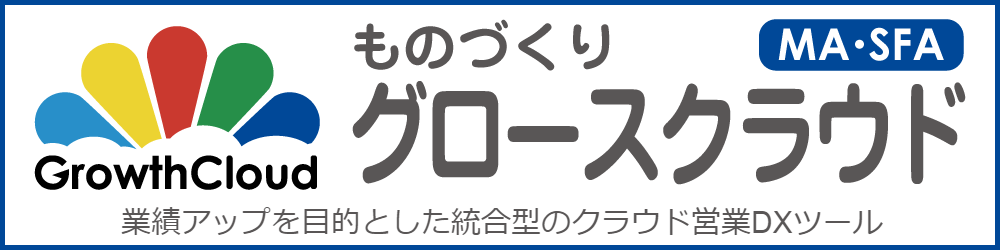片山和也の生産財マーケティングの視点【ランチェスター戦略の新たな解釈】
先週の金曜日、船井総合研究所の大阪本社で、機械工具商社経営研究
会の2月度定例会が開催されました。全国から地域一番店クラスの機
械工具商社が集まるため、全国の市況や今後の見通しがつかめます。
↓↓↓機械工具商社経営研究会2月度定例会の様子
https://katayama.typepad.jp/blog/
各社に共通していることとして、どれほどの優良会社であったとして
も、売上のベースは確実に下がっている、ということです。
売上というのは「ベース」と「スポット」に分けることができます。
「ベース」というのは、例えばスペック・インしている様な部品や、
日々流れる切削工具・消耗品のことを指します。
それに対して「スポット」とは、継続しない文字通りスポットの受注
のことを指します。
「ベース」の商売というのは安定している反面、どちらかと言えば
“守り”の商売です。国内の生産財マーケットが確実に7掛け未満と
なっている以上、「ベース」が落ちる、というのは当然のことだと思
います。
「スポット」の商売は受注が継続しない反面、“攻め”の商売であり、
本当の意味での営業力・売る人の人格が問われます。下がる「ベー
ス」を補える「スポット」が受注できるかどうかが、現在の市況を乗
り切る一つのポイントです。
つまり、下がっている「ベース」を押し上げようと営業努力を重ねて
も、はっきり言ってまず結果はでません。それよりも新しい商品を売
り込むか、あるいは新しい顧客に売り込むか、そのどちらかを全社を
挙げて推進していくしかない、ということです。
また、どの様な会社においても情報発信の総量が、その会社の売上に
比例します。例えば電動シリンダ(ロボシリンダ)を展開するIAI
社は現在においても業績が好調だといいます。同社は3年前に、全国
の販売店に対してデモ機を貸し出し、120件以上のアンケートをユ
ーザーから獲得すればデモ機を無償供与する、という大々的なキャン
ペーンを行いました。また無料小冊子や様々な新しい営業ツールを投
入しました。
その時の販売店の営業マンの声は、「アンケートはとれたけど売れな
い」「実際の数字に結び付かない」と、現場の評価は散々でした。
しかし私は、現在の同社の好調は、この時のエンドユーザーへのキャ
ンペーンが大きく貢献しているのではないかと思います。
B2Bビジネスの場合、行ったことがすぐに成果には結び付かないか
もしれませんが、遅くとも2年以内には成果につながる様な気がしま
す。
さらに最近、私が強く感じていることは「地域密着」というスタイル
の限界です。例えばランチェスター戦略、という考え方があります。
ランチェスター戦略の根幹は、自社が「強者」であるのか「弱者」で
あるのか考え、自社が「弱者」なのであれば“広域戦”ではなく“局
地戦(=ゲリラ戦)”に持ち込む、という考え方です。
リーマン・ショック以前であれば、
広域戦=全国区
局地戦=地域密着
だったと思います。しかし現在の生産財業界を見ていると、
広域戦=海外展開
局地戦=広域商圏・全国区
といった感じではないでしょうか。
事実、最近の船井総研のセミナーDMのタイトルを見ても、「地域一
番店」というタイトルが、ほとんど見られなくなりました。「地域一
番」だけでは生き残れない、ということなのです。
従って、広域エリアに商圏を広げる「多拠点戦略」か、利益率が上が
る取り組みを行う「高付加価値戦略」か、いずれかの戦略を選択する
必要があります。
いずれにせよリーマン・ショック以降、完全にルールが変わったと考
えるべきなのです。
生産財マーケティングのことなら生産財マーケティング.COM>>> https://seizougyou-koujoukeiei.funaisoken.co.jp/
製造業・工場経営の最新ノウハウ資料を見る