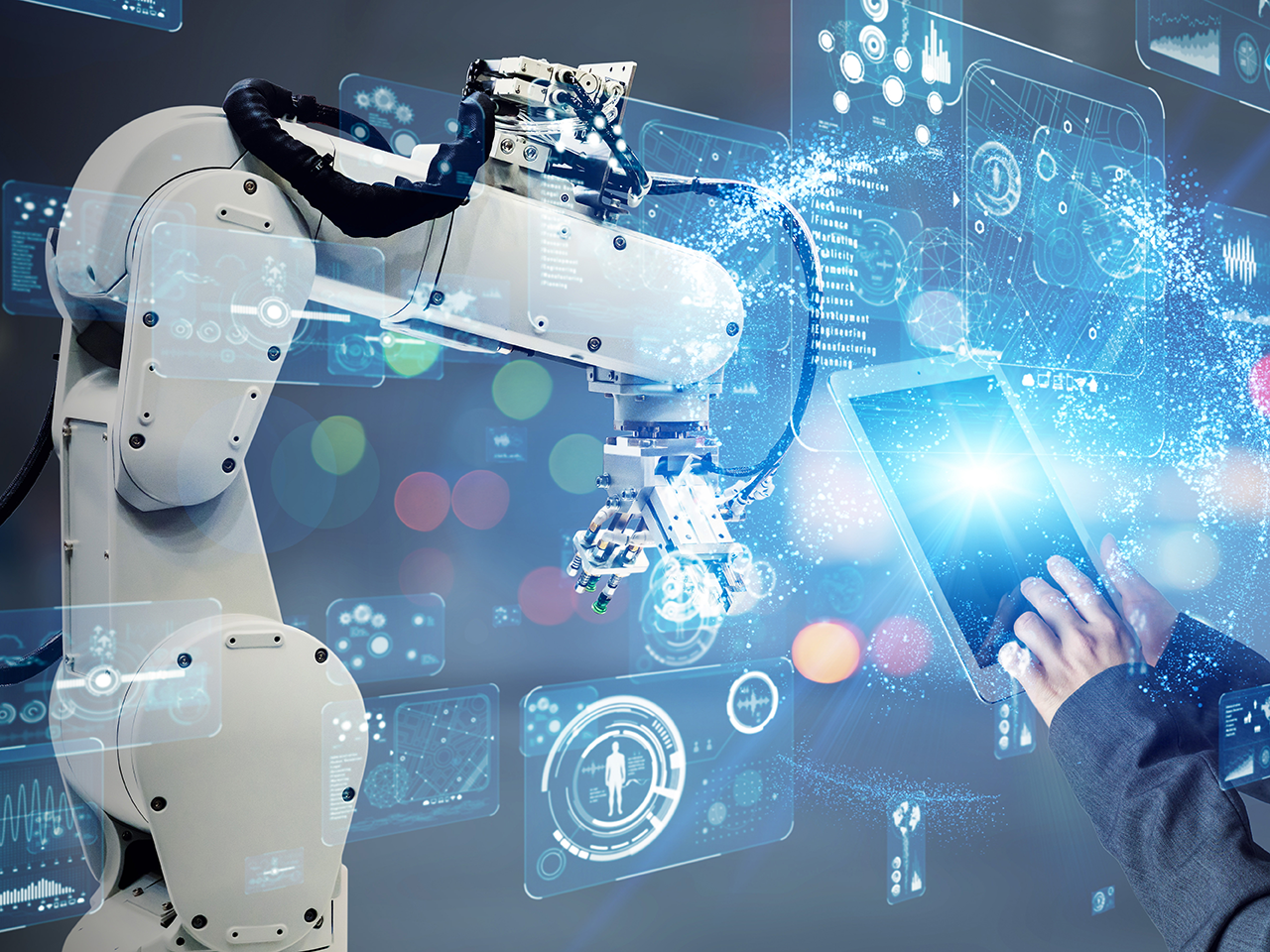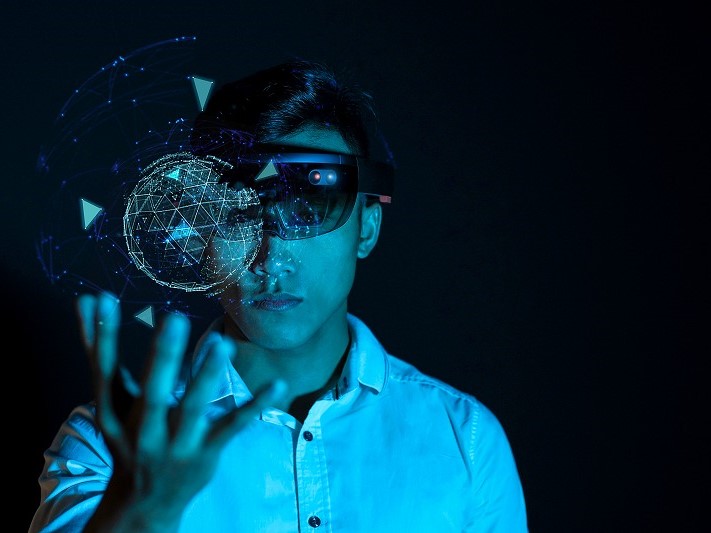新年あけましておめでとうございます。
本年もファクトリービジネスレポートを引き続きご愛顧のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
東京大学大学院教授の吉見俊哉氏は、同氏の著書「大予言「歴史の尺度」が示す未来」の中で、歴史はある一定の周期で変化を繰り返しており、マクロにみればある程度の未来予測、言い換えれば予言が可能だと述べています。
まず、吉見教授によると歴史は25年周期で変化が見られるといいます。それによると1995年~2020年は「衰退と不安の25年」であり、日本が終戦を迎えた1920年~1945年の「経済恐慌と戦争の25年」に匹敵する時代であったと考察しています。
ちなみに、この25年周期を足した50年周期説が、有名なソ連の経済学者ゴンドラチェフの波です。
さらに吉見教授は、この25年周期に加えて、歴史はさらに長い単位にあたる500年周期の波があるといいます。これは歴史家フェルナン・ブローデルの名前をとって、「ブローデルの波」と呼ばれます。
歴史家ブローデルは自著の中で次の様に述べています。
“経済学の領域におけるここ20年か30年の最も重要な発見は、時間の座標の発見、経済活動の周期性の発見である。”
例えば21世紀の現在、世界はゼロ金利であり日本をはじめ世界中がカネ余りの状態です。市場が飽和し、新たなフロンティアが失われた結果、先進国を中心に世界中がデフレに陥っているわけです。
同じ状況が500年前の16世紀にもみられました。ジェノバの「利子率革命」がそれです。
この革命は、当時の世界経済を牽引していたイタリアのジェノバで金利が極度に低くなっていった状況を指します。この時代、イタリアの銀行にはスペイン皇帝が新大陸で得た大量の銀が集まっていました。しかし投資が隅々まで行き渡ってしまったことで、資本がだぶついているのに投資先がない状態に陥ります。
一般に、利子率が2%を下回れば、資本側が得るものはゼロであり、そのような超低金利が10年を超えて続けば既存の経済・社会システムは抜本的な構造改革を迫られると同書は指摘しています。
ちなみに、日本の国債利回りは既に20年以上も2%以下という超低金利が続いており、「経済史上、極めて異常な状態に突入している」のです。
なお、日本が徳川時代に鎖国を行った理由は、キリスト教化を防ぐという理由もありますが、この様に16世紀は世界的に経済が収縮期であり、国際貿易を行うメリットがそれほどなかった、ということも大きな理由と考えられています。
この様に、主に25年周期と50年周期の知見から、同書では2020年以降を次の様なマトリックスで設定しています。
・2020~2045年 収縮期
矛盾の激化と構造改革の努力、日本社会の変革期
・2045~2070年 拡張期
日本における危機の小康、全世界的な危機の進行
※ちなみに、コンピューター(AI)の知能が人間の知能を凌駕すると言われるポイント、シンギュラリティ(Singularity)が発生するのは2045年と予測されています。
・2070~2095年 収縮期
全世界的な資本主義の危機と新しい社会への模索
・2095年~
持続可能なポスト資本主義社会への緩やかな移行
詳細は同書を一読いただければと思いますが、同書によると特に日本の近未来は悲観的です。また様々な示唆は得られるものの、ビジネス的な具体策が提示されているわけでもありません。
その点で、2018年にあらゆる経営者が押さえておくべきポイントは次の2つだと私は思います。
1.デジタル化
2.多様性の受け入れ
昨年10月、毎年恒例のグレートカンパニー視察セミナーで米国東海岸(ボストン・ニューヨーク・コネチカット)のグレートカンパニーを視察しましたが、中でも私が強く示唆を受けたのはブルームバーグ社です。
昔のニュース番組ではよく「ロイター発共同によると・・・」と、国際通信社であるロイターの名前がよくでてきました。ところが現在よく見られるのはブルームバーグです。
それもそのはずで、ロイターは記者によるストライキが頻発して経営危機に陥り、現在ではカナダのトムソン社の傘下に入り、トムソン・ロイターと社名も変わっています。
ではなぜロイターは衰退し、ブルームバーグは覇権を握ったのか。
それはロイターが記者という属人を中心とする通信社であったのに対し、ブルームバーグは社員の1/4がエンジニアで自社を「テクノロジー企業」と定義する、デジタル企業だからです。
ブルームバーグの主な収益源は“ブルームバーグ端末”と呼ばれる情報インフラの端末であり、世界中に32万5000ものクライアントを抱えています。同社は経済誌の発行やテレビ番組、Webサイトの運営など様々な事業を手掛けていますが、確固たる収益源はこの“ブルームバーグ端末”なのです。
あらゆる業界にとって、この「デジタル化」への対応は避けて通れないものになっています。
以前、このコラムでも取り上げましたが今、注目の本に「対デジタル・ディスラプター戦略 既存企業の戦い方」(日本経済新聞出版社)があります。
一夜にしてタクシー会社から顧客を奪ってしまうウーバー、同様にホテル・旅館から顧客を奪いつつあるエアビーアンドビーなど、デジタルを武器にする新興企業が成熟産業の顧客を奪い取ることが日常となりつつある中で、既存企業はいかにこうした新興企業に対抗していくべきか、ということを述べているのが同書です。
その中で同書の主張は「円熟した企業にはいまでもかなりの価値があり、業務と主要な内部プロセスをデジタル化することで、そうした価値を引き出せる」というものです。
私の専門分野はBtoBの製造業ですが、多くのBtoB企業にとってデジタル化すべきプロセスは「営業」であるといえます。一見、成熟産業に見える業種・業態でも、「営業のデジタル化」を進めることで今までつかめなかった様な顧客ニーズを把握することができます。
またデジタル化と同様に、「多様性の受け入れ」もこれからの経営環境には必須です。
「多様性の受け入れ」とは一言でいえば「働き方改革」です。残業を無くし、年間休日を増やし、仕事とプライベートを両立できる働き方を推奨できる会社・組織でなければ生き残れない時代が明らかにやってきています。
正直に言えば、私も根本は昭和の人間ですので、残業をするな、休日は休め、という「働き方改革」には生理的に違和感を覚えます。
しかしこれも「時流」ですので、経営者は「時流適応」できなければ生き残ることはできません。
今まで10の時間をかけていた仕事をいかに8の時間で質を落とさず、もっというと質を上げて行うのか、そして空いた2の時間を自己研鑽なり余暇なりにあてるという働き方改革を、組織トップ自らが考えて実行しなければならない時代が2018年です。
ちなみに、前述の「大予言「歴史の尺度」が示す未来」に話を戻しますが、同書によると世代間の距離はだんだん小さくなっているといいます。例えば戦争世代と第一戦後世代の世代間の差が0.19とすると、団塊ジュニアと新人類ジュニアの世代間の差は0.03だといいます。
また親子の差が1973年は0.31だったのに対し、2003年には0.06、さらに2008年になると△0.01という、親子の世代間の差はほぼ消失してしまったという驚くべき結果がでています。
従って我々も「今の若い世代は理解できない」と口にすることなく、前述のデジタル化と働き方改革を粛々と進めていく必要がある、ということなのです。
製造業・工場経営の最新ノウハウ資料を見る