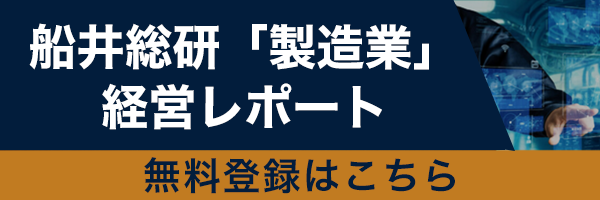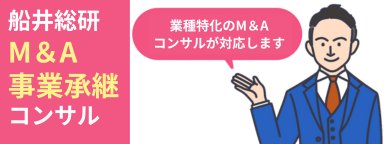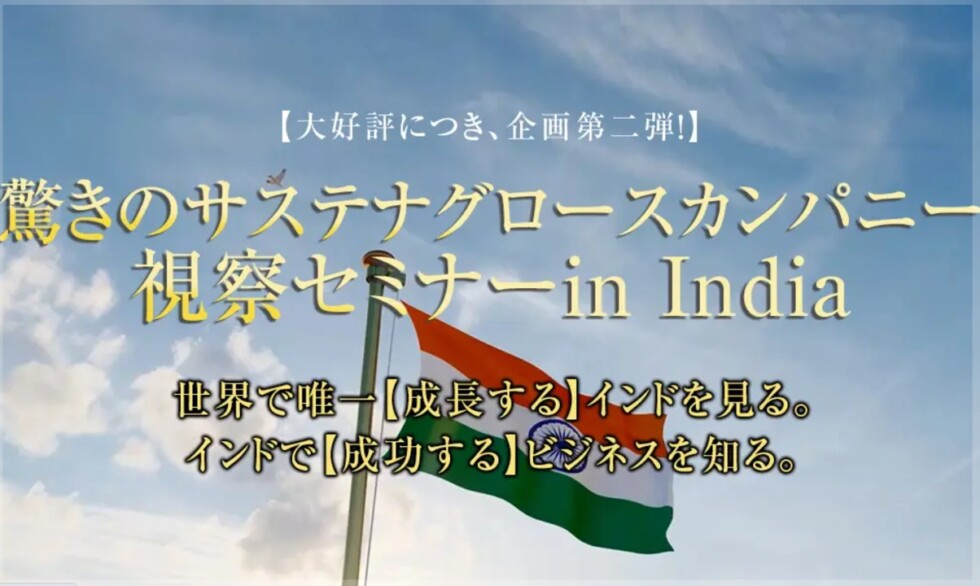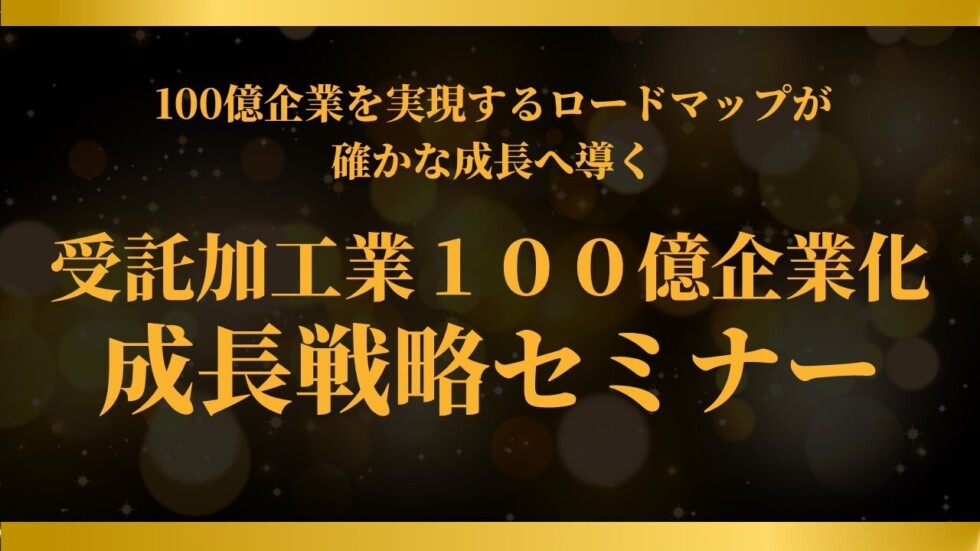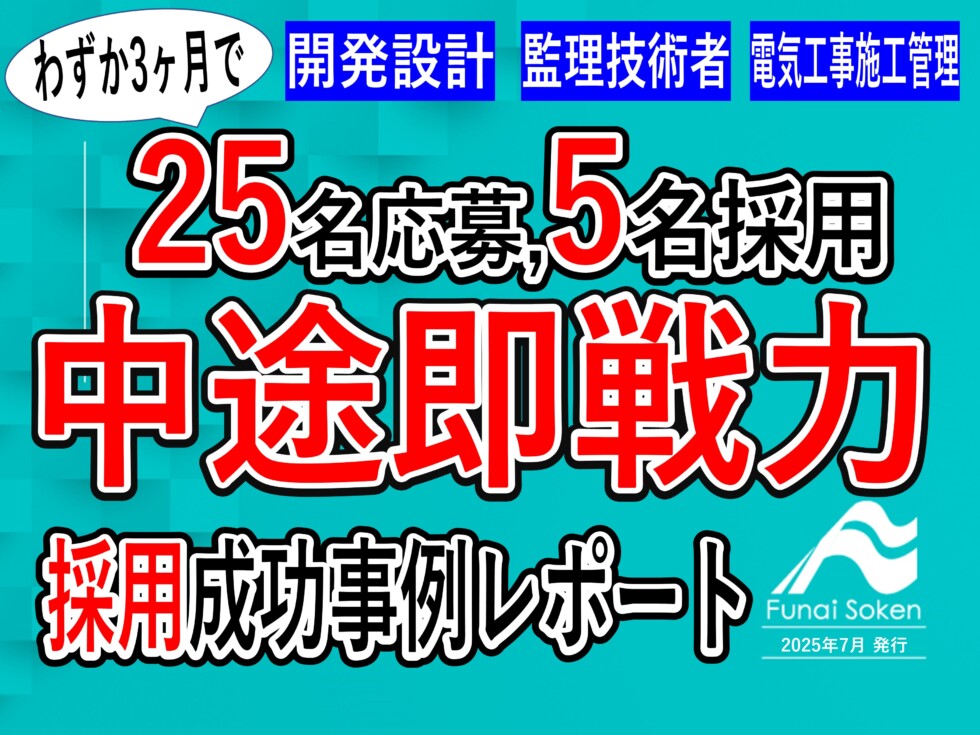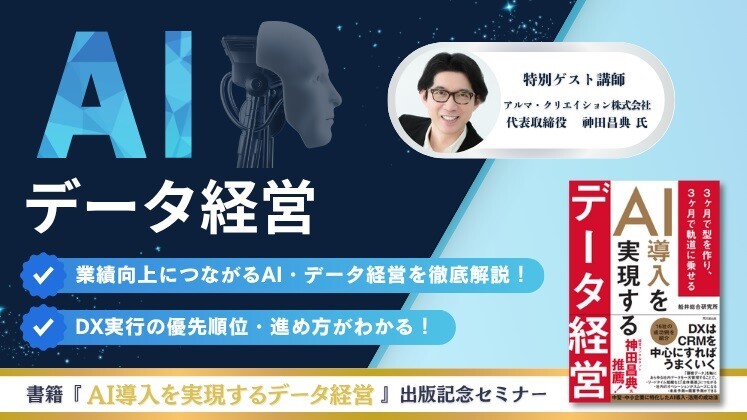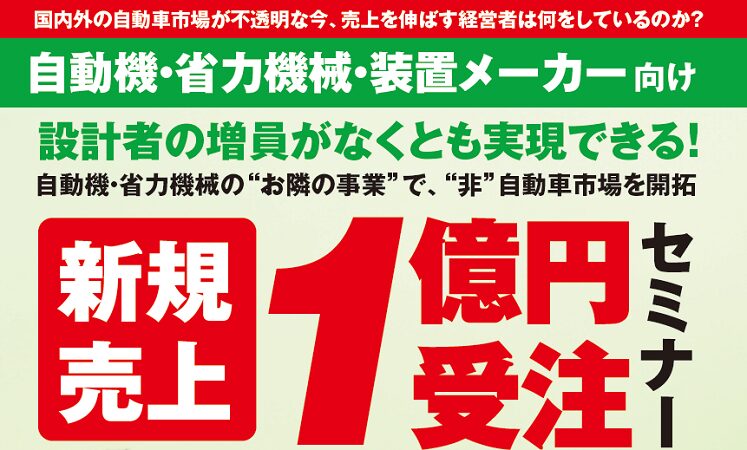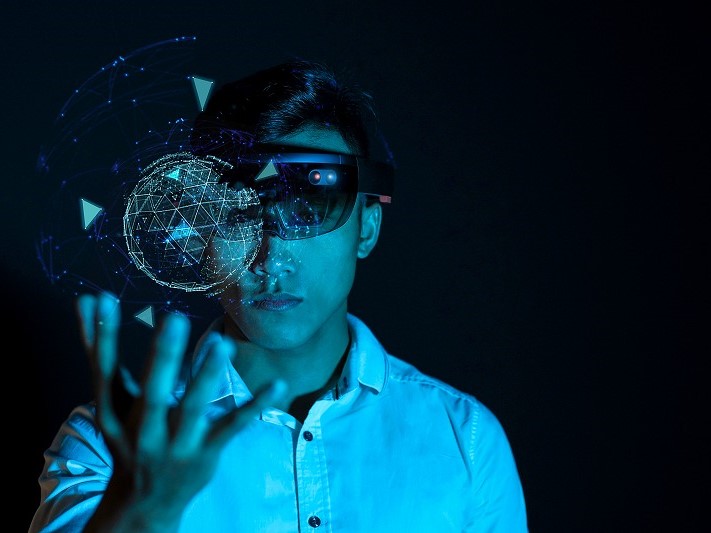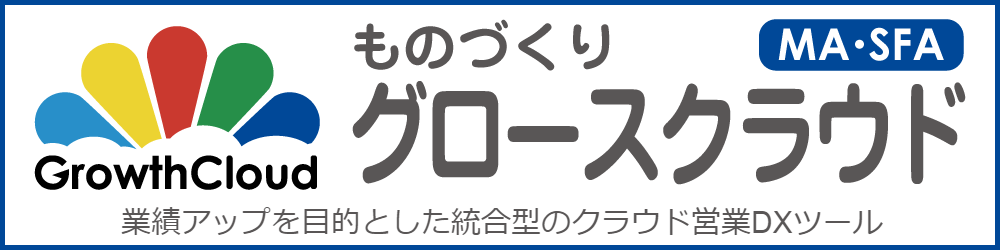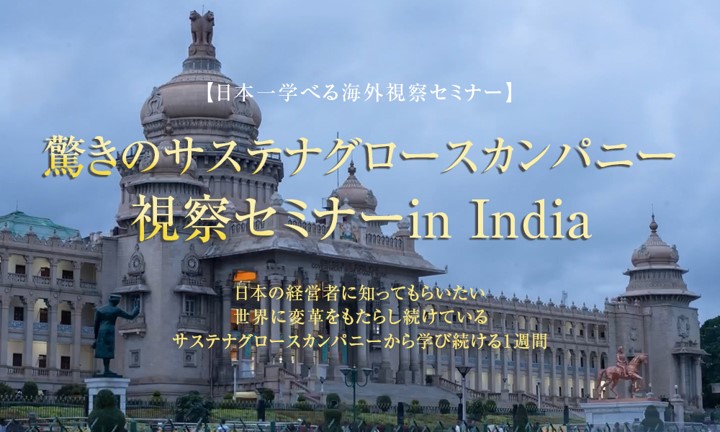
「失われた30年」をもたらした「7/24」とは何なのか?
先月の初旬、経営者60名の方とインド視察セミナーを開催しました。
船井総合研究所が主宰する海外視察セミナーとしてインドでの開催は初めてということもあり、定員50名のところ、お申し込みが重なり、前述の通り60名での実施となりました。
2024年の世界経済成長のIMF統計によると、世界全体の経済成長率が約3%、米国も約3%で中国が約5%、日本やドイツに至っては0.3%とほぼ0成長かマイナス成長であるのに対して、インドは7%近い成長率でした。
「今、成長しているインドを見にいく」という意味合いもありますが、今回のインド視察はもっと深い意味があります。
その1つのキーワードが「7/24」です。
「7/24」は、「セブン・パー・トゥエンティフォー」と読みます。
つまり“7日間(1週間)・24時間休まず仕事をこなす”という意味です。
この「7/24」とは何なのかというと、主に米国のソフトウェア開発で用いられている概念です。
インドと米国は時差が13時間ありますから、米国の昼間はインドの夜です。
こうした時差をうまく活用すると、米国が昼間の間にシステムの仕様を決定し、夕方にその開発をインドに依頼します。
米国の夕方はインドの朝ですから、米国が夜のうちにインドで開発が進み、米国が翌朝の段階でインドから完成したシステム(ソフトウェア)が届くことになります。
これが「7/24」の概念です。
米国などはここ30年、この「7/24」を活用して経済成長を遂げてきました。
今、米国の大手テック企業のCEOにインド人が多いのは、これが理由です。
それに対して、日本の場合は新興国との価格競争に巻き込まれ、この「7/24」という概念が希薄でした。
この違いが日本に「失われた30年」をもたらしたのではないかと私は思います。
中国とは異質の競争力・将来性を持つ国、「発展途上国でありながらIT・DX先進国」インド
今回、60人の経営者の方とともにインドを視察しましたが、そこで私が強く感じたのは「中国とは異質の競争力」の強さです。
具体的には、
1)インドは英語圏である
インドは州が異なると別の国と同じで、20を超える公用語があります。
その結果、インドの公用語は事実上英語であり、大学卒業者であれば、英語が普通に通じます。
したがって、欧米とコミュニケーションが容易である、というのは大きな強みです。
2)優秀な理系人材が圧倒的に多い
インドは日本と異なり、大学の大半が理系大学です。
例えば、IIT(インド工科大学)とよばれる国立の工業大学がインド国内には27校あります。
今回、その1つであるIITマドラス校を視察しましたが、世界トップレベルの教育が行われています。
米国のシリコンバレーがスタンフォード大学の存在によって成り立っていますが、インドの場合もIITに代表される超優秀な大学が頭脳の供給源になっているわけです。
3)人件費が安いが、自動化に熱心である
インドの人件費は日本の約1/5の水準です。工場のワーカーだと日本円で年収50万円ほど、大卒のソフトウェア技術者だと150~200万円といった水準です。
では、人件費が安いから人海戦術で、ものづくりにあたっているかというと、そうではありません。
今回視察した中国・韓国メーカーの下請けを行っているテレビ部品工場では、社内の生産技術部門がファナックのロボットを使った自動機で、自動組み立て装置をラインに投入していました。
また、今回視察した二輪工場でも、機械加工や塗装工程はほぼ全自動。
多数のAGVが工場を走り回り、先進国の工場と比較して遜色はありません。
かつての中国の場合は、北京オリンピックの前は工場もほぼ人海戦術であり、それこそボール盤がラインにずらっと並び、安い汎用機で人海戦術の仕事をしていました。
優秀な理系人材(エンジニア)をふんだんに供給できるインドは、当時の中国よりもはるかに高い潜在力があります。
4)発展途上国であるが、ITやDXでは日本より先行している
前述の「7/24」に加え、インドは英語圏ということもあり、インドには米国のグーグルやマイクロソフト、アマゾンといった超先進な会社からの高度な仕事が流れ込んできました。
こうした仕事をこなす中で、インドのソフトウェア技術は米国と遜色のないものになっています。
「発展途上国なのにIT・DXでは先進国」というギャップが、インドの特色です。
5)親日的であり、日本のことをリスペクトしている
中国や多くのアジア諸国の場合、先の戦争(日中戦争・太平洋戦争)の影響もあり、まだ若干のしこりが残っています。
ところが、インドの場合はこうした戦争の影響がほぼ無いこと、むしろ日本はインドの独立を支援していた経緯もあり、基本的に親日であり、かつ日本のことをリスペクト(尊敬)している人も多いです。
「日本に行きたい」「日本で働きたい」と、日本語を勉強しているインド人も多数います。
こうしたインド市場ですが、今回のインド視察に参加された経営者の方の目的は次のようなことだった様です。
参加した目的1:今後、中国に続き覇権を取る可能性が高いインドの実情をこの目でみる、感じる
・・・今後の自社の戦略・ポジションを練る
参加した目的2:近い将来、インドへの進出を検討している
・・・インドをマーケットとして捉えている
参加した目的3:インドでの人材採用・開発拠点の設置を検討している
・・・インドを仕入先として捉えている
インド視察ですが、今年の年末~来年早々にも、第二弾の実施を企画しています。
もちろん私も、講師として参加の予定です。
ぜひ、ご期待いただきたいと思います。
「7/24」はインドだけではない
なお、今回お伝えしているキーワード「7/24」は、インドを活用する、ということだけではありません。
例えば、私の関係先の機械加工業J社の場合、ここ2年ほどの設備への自動化投資の結果、1人あたり生産性を1.5倍ほどに高めることに成功しています。
これは自動化設備を活用して「7/24」を実現したケースです。
あるいは「自社のソリューションサイト」を自社の営業担当者の代わりに24時間・365日稼働させることにより、2年半で新規商談創出15億円・新規受注1億円という事例もあります。
また生成AI(ChatGPT)をチャットボットとして自社のソリューションサイトに実装させることで、顧客数を3倍にした事例もあります。
こちらはDXを活用して「7/24」を実現したケースであるといえます。
なお、このDX活用による成功事例は、こちらのYoutubeチャンネルに30本以上の無料動画としてアップされています。
このゴールデンウィークの期間、ぜひ、こちらのYoutubeチャンネルをご覧いただければと思います。
<Zoho成功事例 船井総研Youtubeチャンネル>
https://www.youtube.com/@zohoyoutube1828/videos
製造業・工場経営の最新ノウハウ資料を見る