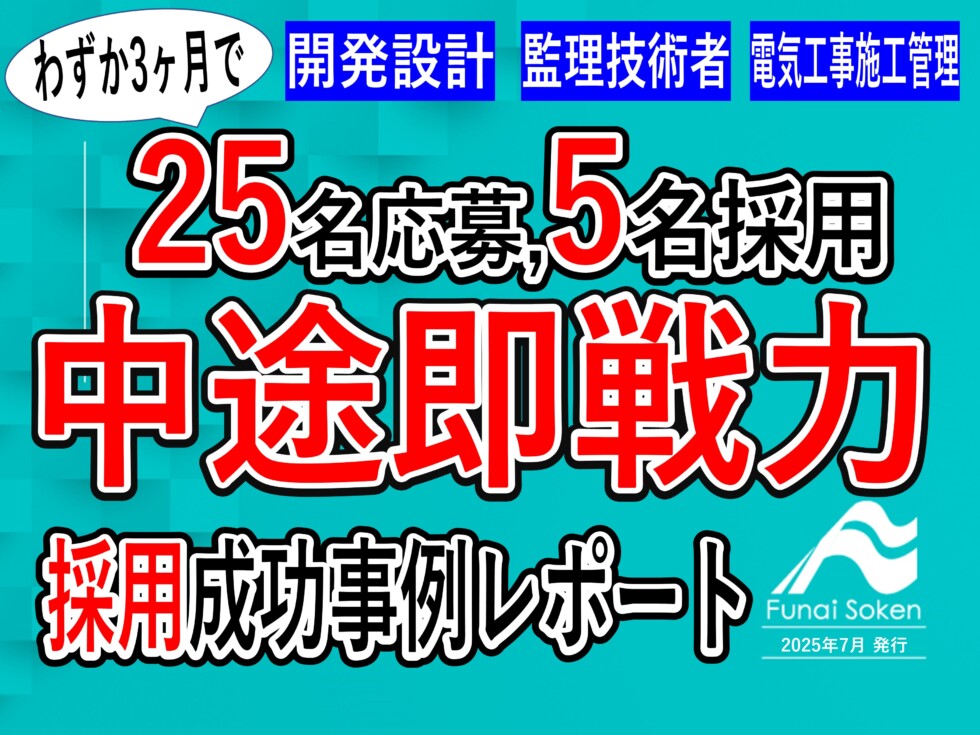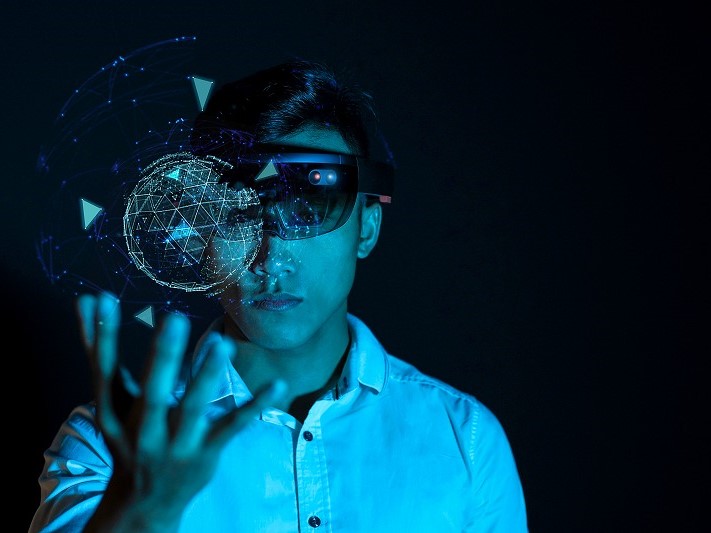2022年もより一層進む寡占化と二極化
2022年は干支でいうと壬寅(みずのえとら)の年にあたります。ダイヤモンドや東洋経済など経済誌では壬寅(みずのえとら)の年を次の様に分析しています。
- 「2022年は今までの常識が覆され、時代にあった新しい常識が模索されはじめる1年になる」
- 「昨年表舞台にたった新勢力が、今年はさらに伸長する」
さて、この干支は60年周期で1回りします。ちなみに昨年2021年は辛丑(かのとうし)、一昨年の2020年は庚子(かのえね)でした。株式投資の世界では年回り(=干支)が市場に大きな影響を及ぼすとして干支を重視しています。
ちなみに昨年、新生銀行を買収したSBIホールディングス代表の北尾吉孝氏も中国古典の専門家として知られ、同氏の著書には「強運をつくる干支の知恵」があります。北尾吉孝氏は慶応義塾大学を卒業後、英国のケンブリッジ大学を卒業しています。
英国という国は研究に値する国で、英国は過去に戦争に負けたことは一度もありません。なぜなら負ける戦争は初めからやらないからです。徹底的に諜報に力を入れて情報を収集した結果、勝てる戦争しかしない。
昨年のSBIホールディングスの新生銀行買収も同様でした。SBIホールディングスは新生銀行へのTOB(株式公開買い付け)を発表。銀行が銀行に対しての敵対的買収は今回が初めてで、当初は徹底抗戦をとなえた新生銀行でしたが、その後金融庁の意向も受けてSBIホールディングスの傘下にはいりました。
SBIホールディングスの北尾氏に限らず、勝てる勝負しか手掛けないのは成功者の鉄則ともいえます。
さて干支に話を戻すと、要は60年周期で同じ様な事象が繰り返されている(=経済周期説・文明周期説)、そこから次の時代の示唆を得る、というのが経営的な考え方です。
実際、近代を振り返ってみても
明治維新(1868年~1889年)
↓ 約60年後
日中戦争・太平洋戦争(1937年~1945年)
↓ 約60年後
東西冷戦終結・同時多発テロ(1989年~2001年)
と、世界レベルでの大きなパラダイムシフトが、だいたい60年周期で起きていることがわかります。
今さらになりますが、東西冷戦の終結は日本の製造業にも大きな影響を与えました。
つまり旧西側、東側、という垣根がなくなったことにより「共産圏」という概念が消え、「新興国」が誕生したからです。具体的にはそれまではクローズな世界であった旧東欧、あるいは中国という労働市場が世界に開放され、「世界の工場」が人件費の安い、かつ10億人のマーケットを有する中国にシフトしていったわけです。
こうしたポスト冷戦の時代に対して、デジタル化による新産業モデルを構築したのがGAFA(グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル)といったビッグテックをつくった米国であり、またインダストリー4.0で新たなサプライチェーンの概念を構築したドイツです。
こうしたデジタル化は急速な寡占と、それに伴う二極化を生み出します。
2022年の企業経営を考える上で、まず私たちを取り巻く現在の時流について再認識したいと思います。
デジタルの時代は「言語圏」で決まる
デジタルの時代に強く意識しておかなければならないことは、デジタルの時代は「言語圏」で決まる、という事実です。デジタル、すなわちソフトウェアの開発というのは映画に似ています。
すなわち、ハリウッドでは大作映画がつくられますが、日本映画ではまず無理です。その理由は「言語圏」にあります。ハリウッド映画が対象としているのは“英語圏”であり、英語圏の人口は全世界で約25億人といわれています(ちなみにこうした英語圏のことをアングロソフィアといいます)。
それに対して日本語圏は約1.2億人。20倍からマーケットが違うわけですから同じ予算がかけられるはずがありません。
同様のことがデジタル(ソフトウェア)の世界にもいえます。
よく「日本ではなぜGAFAの様なビッグテックが生まれないのか?」「日本はもっとイノベーションに力をいれなければならない」といった議論がきかれますが、日本からビッグテックが生まれない理由は前述の通り「言語圏」の問題です。
例えばインターネットの検索エンジン。ヤフーもいまや開発をやめ、グーグルの検索エンジンをつかっています。こうしたAIやクラウドを伴う技術開発は非常にコストがかかるため、世界レベルで寡占化が進むわけです。ましてや言語圏の小さな日本では、それだけの開発費をかけることができないわけです。
米国のGAFAに対抗するのが中国のBAT(バイドゥ、アリババ、テンセント)ですが、英語圏(アングロスフィア)に次いで大きな言語圏を持つのが中国語圏です。中国語圏は全世界で約15億人といわれていますが、米国と中国でしかビッグテックが成り立たないのはそういうことです。
実際、私たちの身の回りでも、昔はあった日本製ソフトウェアが次々に姿を消しています。
例えばワープロソフト。私が学生時代のことは、まだ日本製のワープロソフトをつかっていた人たちが身の回りにいました。彼らがいうのは「日本語への変換機能がよい」とのことで、日本製のワープロソフトを愛用していましたが、現在はほぼ全ての人がマイクロソフト製のワードをつかっているはずです。
また一昔前は日本製のSNSや日本製の動画サイトが流行ったこともありましたが、現在はほとんどの人がフェイスブックやインスタグラムといったSNSを愛用し、また動画サイトもほぼYoutubeに寡占されています。英語圏のソフトウェアの開発スピードと質に追いつかないのがその理由です。
これが現在の様に「クラウド」の時代になると、さらにその傾向に拍車がかかります。
なぜなら「クラウド」のソフトウェアは開発に膨大なコストがかかるからです。
例えばSFA・CRM・MA系のSaas(ソフトウェア・アズ・ア・サービス)といわれるサービスは、全世界でほぼ次の2社しか存在しません。2社とも英語圏のプロダクトです。
- セールスフォースドットコム(米国)
- Zoho(ゾーホー)(米国・インド)
また最近は日本製のクラウドサービスも、よくコマーシャル等で流れています。一見、日本製のプロダクトに見えますが、実はPaas(プラットフォーム・アズ・ア・サービス)と呼ばれるクラウドの開発環境の上で開発されたプロダクトが大半です。
このPaasを提供する会社も世界中でほぼ3社しかなく、しかも全て米国の会社です。
- アマゾン・ウェブ・サービス(AWS)(米国)
- マイクロソフト・アジュール(米国)
- グーグル・クラウド(米国)
ちなみにアマゾンはインターネット通販の会社ですが、本業のインターネット通販は長年赤字が続いていました。同社が黒字化できたのは上記のAWSというサービスを展開していたからです。現在でも、アマゾンの営業利益の半分以上はAWSがたたきだしています。
つまりアマゾンは本業のインターネット通販で儲ける必要が無く、もともとは自社向けのプラットフォームサービスであったAWSが同社の収益の柱です。
またマイクロソフトが復活できたのはクラウド事業のおかげ、といわれますがそれが上記のマイクロソフト・アジュールとよばれるサービスです。
新聞や雑誌等ではこれらサービスのことを単に「クラウド事業」と呼んでいますが、正確にはPaas事業です。つまりデータセンターをただ貸し出しているのではなく、あらゆるソフトウェアの開発環境を提供している、そういうサービスなのです。
ここまでの話で、いかにデジタルの世界は米国が主導権を取っているかがよくわかります。
では日本語圏の我々がいかに勝負していくべきなのか、については後ほど述べたいと思います。
歴史を動かす原動力は「イノベーションのジレンマ」
さらにこうしたデジタルの進展は、これから述べる「イノベーションのジレンマ」を様々なジャンルで誘発します。
では「イノベーションのジレンマ」とは何でしょうか?
例えば自動車産業を例に取ります。
かつてBIG3(GM、フォード、クライスラー)といわれてたアメリカの自動車メーカーは世界で最も儲かっている会社の1つでした。しかし現在は見る影もありません。では、なぜそうなったのか?
アメリカは国土の広い国です。国土が広いのでエンジンの排気量が大きければ大きいほど楽に運転ができる。しかもガソリンも安いので4000ccや5000ccといった車が飛ぶように売れました。
こうした5000ccクラスの自動車というのは安くても400~500万円くらいはします。
では、こうした車が日本の様な小さな島国でかつガソリンを100%輸入に頼っている様な国で売れるかというと絶対に売れません。
ですから日本のカーメーカーは1000ccクラスの車を開発せざるを得ませんでした。具体的にはトヨタのカローラや日産のサニークラスの車です。
こうした1000ccクラスの車は高くても150万円前後でつくらないと売れないでしょう。
では、米国の5000ccの車と、日本の1500ccの車と、製造するのはどちらが大変か?
手間はそれほど変わらないでしょう。何だったら、日本の1500ccの車の方が小さい分、手間がかかるかもしれません。
ところが、手間はそれほど変わらないのに得られる利益はまるで異なります。
400~500万円くらいで売れる5000ccの車だと、おそらく100~200万円前後くらいは手元に利益が残るでしょう。しかし150万円でしかうれない1500ccの車だと手元に20~30万円ほどの利益しか残りません。
では、それまで5000ccの車をつくって200万円の利益を得る体質の米国の自動車メーカーが、同じ手間がかかるのに1500ccの車をつくって20万円の利益を得る体質の会社に変われるか?
絶対に変われません。
米国の自動車メーカーが日本に駆逐された理由はこうした理由です。「アリがキリギリスになる」のは簡単ですが、「一度キリギリスになってしまうとアリには戻れない」のです。
こうした現象を「イノベーションのジレンマ」と呼びます。
さらに自動車業界で今、進んでいるイノベーションのジレンマは「内燃機関」から「EV」へのシフトです。
内燃機関からEVになると自動車の部品点数が半分になるだけではなく、従来はカーメーカーの差別化要素であったエンジンが不要になるため、自動車産業への参入障壁が劇的に下がることがその本質にあります。
イノベーションのジレンマ的に考えると、これから自動車産業で主導権を持つのは、完成車メーカーから部品メーカーになるかもしれません。
イノベーションのジレンマは自動車産業だけではありません。IT業界にも同じ現象が見られます。
例えばかつてのIBM。IBMはもともと1台数百万円する様なメインフレームとよばれるコンピューターで儲けている会社でした。
ところが時代が進み、1990年代に入るとパソコンが登場。それまでメインフレームあるいはワークステーションとよばれていた高額なハードウェアではなく、数十万円と安価なパソコンでシステム構築を行う流れになると、IBMは大きな経営不振に陥りました。
このパソコン時代に大いに儲けた会社が、パソコンのCPUを提供していたインテルです。
ところが2010年代に入ると、パソコンから徐々にスマホの時代に移っていきます。
パソコンの平均単価は数十万円。しかしスマホの平均単価は数万円。
それまでパソコンにCPUを供給していたインテルからすれば、スマホ向けのCPUはとても儲かるビジネスではありません。ですからインテルはスマホ向けのCPUに対しては本格参入を行いませんでした。
そこでインテルの代わりにスマホのCPUに参入してきた会社がクアルコムという会社です。
パソコン向けのCPUと違い、もっと安価につくらないと元がとれないスマホのCPUをつくるため、クアルコムは開発とマーケティングに特化して、全ての製造プロセスは台湾の安い会社に外注することにしました。
その台湾の会社こそが現在のTSMCです。
かつて世界シェアの大半をおさえていた日本の半導体メーカーはNECや東芝ですが、彼らも半導体を製造すると同時に自社ブランド商品も保有していました。これに対してTSMCは下請けしかしませんから自社ブランド商品は持っていません。
日本の半導体メーカーは自社商品を持っているが故に、ライバルになる可能性のあるアップルやクアルコムといった会社が外注にだすことはあり得ません。技術論云々の前に、日本の半導体メーカーが淘汰されてTSMCが主導権を取ったのはこうした構造です。
また、こうした半導体を製造する為の半導体露光装置(ステッパー)は、世界で最も精密な機械といわれています。この半導体露光装置をつくれるメーカーは世界で3社しかありません。
日本のキヤノンとニコン、そしてオランダのASMLです。
10年ほど前まではキヤノンとニコンが世界シェアの8割を握っていました。
ところが現在は、世界シェアの8割をオランダのASMLが握っています。
その理由は単純で、もともとニコンのメイン顧客はインテルだったからです。インテルがCPUのシェアを落とすと同時に、また日系メーカーがシェアを落とすと同時に両社も世界シェアを落としていったのです。
これに対して古くからTSMCに装置を供給していたのがASMLです。またアジア通貨危機の際、日本のメーカーはみんな韓国や台湾などアジアのメーカーから手を引きました。この時に政府から債務保証をとって韓国のサムソンや台湾のTSMCに肩入れしたのがオランダのASMLです。
やはり、技術論云々の前に、ASMLが世界シェアの8割を握っているのはこうした構図が背景です。
ちなみにASMLというのは、いわば「ヨーロッパ連合」みたいな会社です。例えばレンズはドイツのツアイス製、制御はドイツのシーメンス製、半導体露光技術はオランダのフィリップス製、といった具合に欧州共同開発、ともいった性質を持つのがASMLです。
「脱炭素」という新たな非関税障壁
さて、日本では「時流適応」といって、その時代の流れに合わせていきましょう、という考え方ですが、それに対して「自らシナリオをつくる」という考え方の人たちが欧州の人たちです。
こうした彼らが考えているシナリオの中心が「脱炭素」です。
例えばドイツの大手自動車部品メーカーであるボッシュ社は、昨年の段階で既に「カーボンニュートラル」を達成しています。「カーボンニュートラル」とは、その企業活動の中でCO2を排出しない、仮に排出したとするならば、その分のCO2クレジットを購入することで相殺する。こうした考え方がカーボンニュートラルです。
余談ですが、米国のEVメーカーであるテスラ社が黒字化したのも、自動車事業そのものの利益ではなく、同社が持つCO2クレジットの販売によるものです。
今後、欧州についてはカーボンニュートラルを達成していない企業からは輸入しない、あるいは輸入するにしても「炭素税」の支払いを義務付ける、こうした流れになることはまず間違いないとみておくべきでしょう。
また欧州には「欧州バッテリー同盟」というのがあります。これはEU域内で使用されるEVについては、全てのバッテリーのリサイクルを義務付ける、というものです。そしてそのリサイクルはEU域内で行われ、EU域内で生産されたバッテリーでなければリサイクルのフローにのせない、というEVのバッテリーに対しての事実上の非関税障壁です。
中小企業もこれから求められるESG
こうした流れの中で、株式公開企業の場合は“ESG”を行っていなければ、今や投資対象から外されてしまう時代になっています。ESGとは、
- E:エンバーロメント 環境
- S:ソーシャル 社会
- G:ガバナンス 企業統治
の略語です。
まずE(環境)の筆頭が「脱炭素」です。例えばCO2排出の元凶とされる石炭火力については、大半の金融機関や投資家が融資を引き揚げるか、あるいは新たな投資を行わないことを明言しています。
またアップルは2030年までに、全てのサプライヤーの「カーボンニュートラルを実現する」としています。つまり株式公開をしている大企業だけでなく、その取引先にもESGが求められる時代になっている、ということです。
ちなみに、CO2の排出が本当に気候変動に影響しているのかどうかというのは諸説あります。例えば縄文時代というのは今よりも5℃くらい平均気温が高かったそうで、一年中ずっと春・夏の状態だったから稲作を行う必要もなく、年中収穫することができる栗や木の実を主食にしていたといいます。平和な時代なので争いもそれほど起こらず、縄文時代は5000年ほども続いたという説もあります。
つまり縄文時代の気温の高さは、CO2の排出とは別次元の要因があったわけです。
しかし、今やCO2が気候変動に影響しているしていないの議論以前に、このESGに対応していなければ投資もされなければ、場合によっては取引も打ち切られる、そういう時代になっていることを経営者としては「時流認識」として捉える必要がある、ということです。
さらにESGのSとG。
S(ソーシャル:社会)については社会貢献もそうですが、コンプライアンスの順守と様々なハラスメントの撲滅。「発言ひとつも気をつけなければならないから、かた苦しい世の中だ」という見方もありますが、見方を変えれば誰もが不快な思いをすることなく暮らすことができる、仕事をすることができる「気配り社会」の実現を目指す、というふうに捉えるべきでしょう。
G(ガバナンス:企業統治)は大企業でいえば社外取締役。中小企業でいえば税理士や会計士、あるいは経営コンサルタントといった、幅広い分野で専門的な知見を持つ専門家の活用(=使いこなす)といったことがより重要になると思います。またESGのGもつまるところサスティナビリティ―(=事業永続)を目的としているわけで、そう考えると中小企業における最も重要なガバナンスとは事業承継であるとも考えられるでしょう。
さて、冒頭に述べた壬寅(みずのえとら)の年のポイントは、繰り返しになりますが改めて下記の通りです。
- 「2022年は今までの常識が覆され、時代にあった新しい常識が模索されはじめる1年になる」
- 「昨年表舞台にたった新勢力が、今年はさらに伸長する」
まさに脱炭素やESG、それに先に述べたデジタル寡占やイノベーションのジレンマがこうしたことに相当するのではないでしょうか。
では今年2022年、私たち中小製造業(部品加工業・セットメーカー)あるいは生産財商社が取組んでいくべきことは何なのでしょうか?
~次回に続く~
製造業・工場経営の最新ノウハウ資料を見る