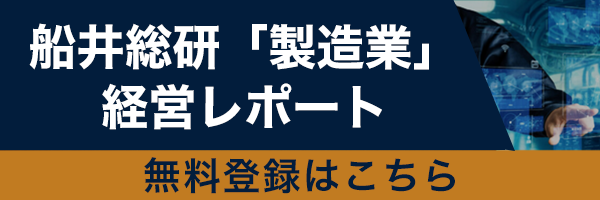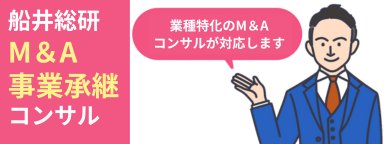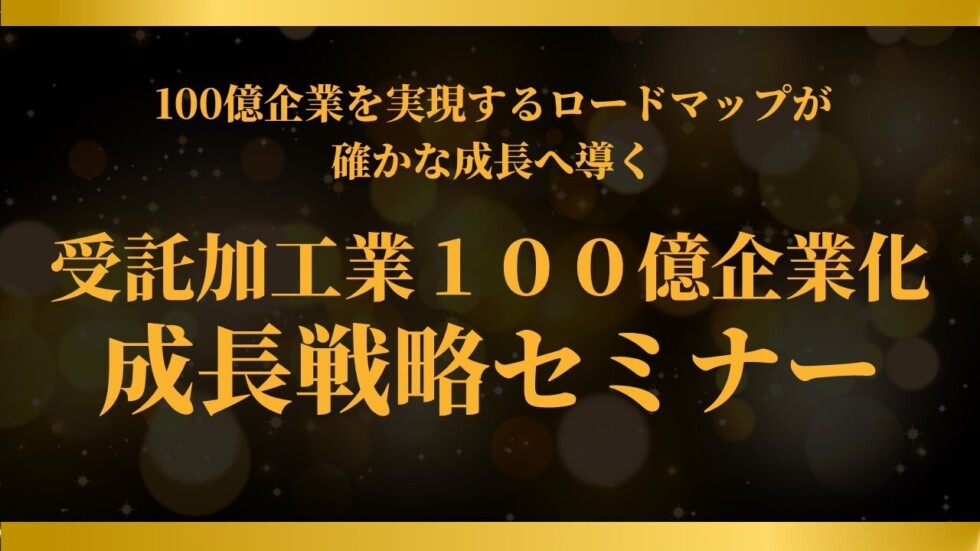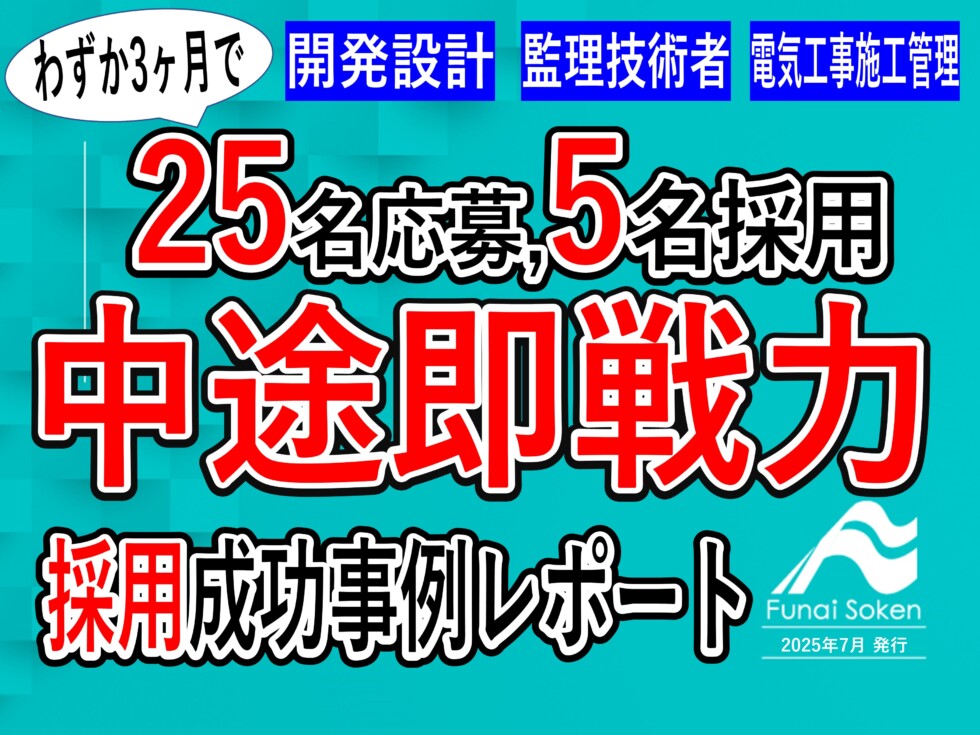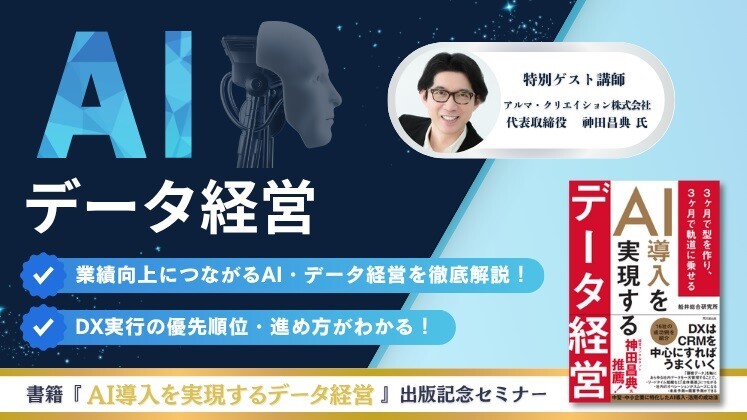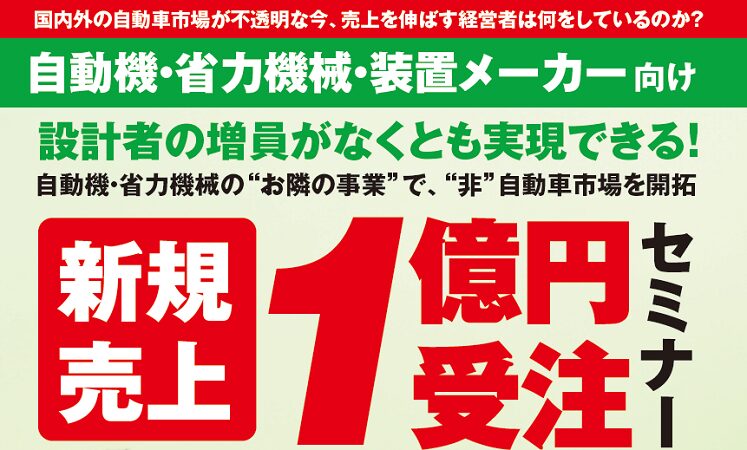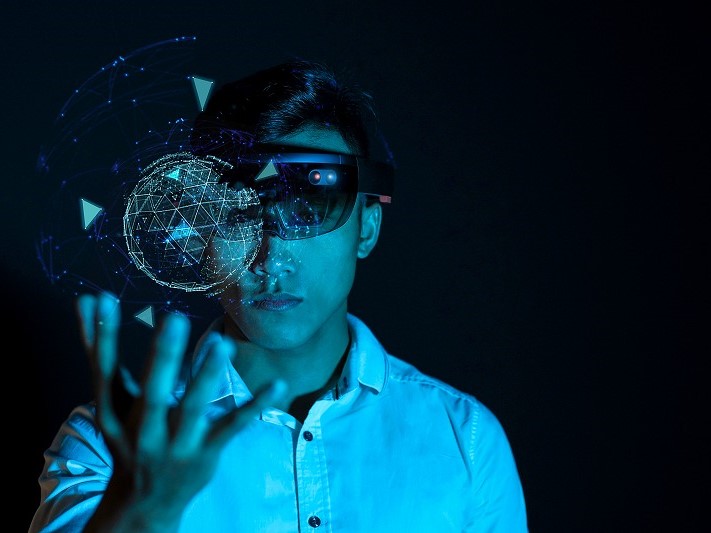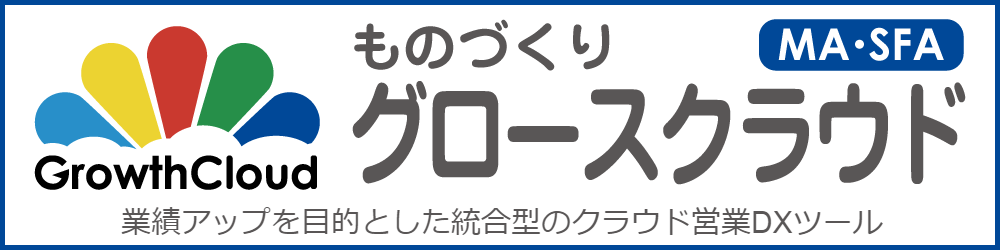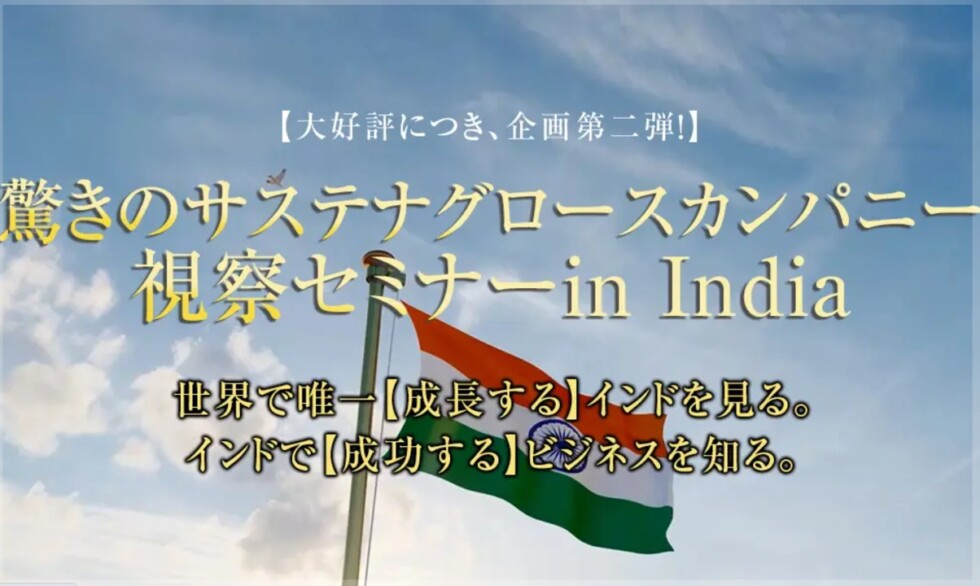
今、注目の1冊「アメリカが仕掛ける世界経済戦争の内幕 CHOKEPOINTS(チョークポイント)」
先日の日経新聞の書評でも紹介されていましたが、日経BPから出版された「CHOKEPOINTS(チョークポイント) アメリカが仕掛ける世界経済戦争の内幕:エドワード・フィッシュマン 著」は、私も読んでみて注目の1冊だと思いました。
本書のタイトルにもなっている“チョークポイント”とは、もともとは地政学的な“急所”を指す言葉です。
その代表例が「マラッカ海峡」です。
欧州からアジアに向かう船は必ずこの海峡を通過しなければならず、この海運の要衝でハブ港湾として栄えたのがシンガポールという都市国家です。
次に、南アフリカの「喜望峰」。
ここも欧州からアジアに船で向かう時の重要な補給地点でした。
日露戦争の際、日本の連合艦隊がロシアのバルチック艦隊に勝利できた背景には、当時イギリス領だった喜望峰が、日英同盟を理由にバルチック艦隊への補給を断ったということが挙げられます。
さらに、太平洋と大西洋を行き来するには、南米南端の「マゼラン海峡」を通過する必要があります。
この近くに位置するのがイギリス領のフォークランド諸島であり、当時、サッチャー政権下のイギリスとアルゼンチンが領有権を巡って「フォークランド紛争」を起こしました。
また、両大洋を結ぶ「パナマ運河」は、事実上アメリカの持ち物です。
さらに、太平洋を横断しようとした時に補給拠点となるハワイ、サイパン、グアムといった島々も、アメリカの統治下にあります。
つまり、世界一周の航路を考えると、必ずイギリス(=大英帝国)かアメリカの領土を通ることになります。
これこそが英米(アングロサクソン)が覇権を握っているバックボーンであり、かつてのチョークポイントだったわけです。
現在のチョークポイントは「ドル決済」
そして昨今、経済をにぎわせているのがトランプ関税問題です。
このトランプ関税問題は、日本の中小企業にも大きな影響を与えています。
特に自動車産業。
関税の影響や、自動車輸送船の入港に関わる港使用料の問題から、自動車を巡るサプライチェーンは不透明な要素が高く、新車モデルの投入が大きく減っています。
その結果、特に自動車関連の金型業界、治工具業界は大きな影響がでています。
金型や治工具は、車の新モデルが投入されないと、新たな発注が発生しないからです。
会社によっては、「リーマンショックの時よりも仕事が激減した」といっているほどです。
しかし本書によると「米国の世界貿易に占めるシェアは1割ほど」だといいます。
つまり、世界貿易の中で米国が占める立場は相対的に低く、関税を武器にして経済戦争を仕掛けたとしても、逆に米国以外の市場に貿易が流れてしまう可能性が高い、といわれるのはこれが理由です。
ところが驚くべきことに、国際決済に占めるドル決済の比率はどんどん上昇しており、本書によるといまや「国際決済の9割をドルが占める」そうです。
米国政府は意図的に「ドル決済」の比率をどんどん高めており、敵対する相手国に対しては「ドル決済圏」からの締め出しを行い、経済的な圧力をかける手法を磨きこんでいるのだといいます。
つまり、現在の最大かつ最強のチョークポイントは「ドル決済」。
これに対して、中国は「レアメタルの輸出」というチョークポイントで旧西側諸国を揺さぶっています。
サプライチェーンにおける世界のレアメタルの7~8割は中国依存であり、日本でもニッケル・クロム系の特殊鋼が値上がるなど、製造業の世界でも影響がでています。
さらにロシアは「ハイブリッド戦争」とよばれる、サイバー攻撃やフェイクニュース攻撃を組み合わせた陽動作戦で敵国を揺さぶる戦略を確立しています。
ロシアが原因なのかどうかは不透明ですが、日本でもアサヒ飲料を始めとする大企業がサイバー攻撃を受け、致命的なダメージを受けています。
このように、ほんの数年前まで世界経済の中心だった「グローバル」は完全に終わりをつげ、今の時代は世界の列強が自国の持つ「チョークポイント」を武器に、経済戦争・覇権を競うようになってしまった。
これが、本書の語る主な文脈になっています。
今、中小企業の経営者が押さえておくべきポイントとは?
このように、今や世界経済のマクロな動きが、地方の中小製造業にまで大きな影響を与える時代になっています。
そして、私自身が経営コンサルタントとして多くの会社を見ていて強く感じることは、大企業であれ零細企業であれ、こうした世界の動きを構造的に、自分ごととして捉えることができている社長が経営する会社が業績を伸ばしている、ということです。
逆に、そこそこの規模であっても、こうした世界の動きを「地方の中小企業の自社とは関係が無い」と、構造的に捉えることができず、動きや思考も従来と変わらない会社は、大きく苦戦しているようにみえます。
抽象論で大変恐縮ですが、ヨットは逆風でも、その逆風をうまく捉えて前進することができます。
前述の「世界の動きを構造的に、自分ごととして捉えている」社長の会社は、こうした「逆風」を「追い風」に変えることができていると思います。
なぜなら、“シナリオ”が読めるので、「今、この会社と取引しておかなければならない」「ここの会社は、これから先、厳しくなる」といった勘が働き、先手を打つことができるようになるからです。
こうした意味で、経営を行うにあたって最も「示唆」を与えられる場の1つが「海外視察」だと思います。
実際、船井総合研究所でも年に数回「海外視察」を実施していますが、この「海外視察」に参加されている参加企業の業績は、同業他社と比較しても明らかに業績が好調です。
そして今、私が最もお奨めしたい「海外視察」の企画が、私も講師として参加しますが、来年2月7日~13日に開催される「驚きのサステナグロースカンパニー視察セミナー in インド」です。
なぜ、船井総合研究所はインドに進出するのか?
考えてみれば、2000年から2020年(=コロナ・ショックの年)までの20年間、世界を大きく動かし、日本にも大きな影響を与えた国は、間違いなく中国でした。
そして、これからの20年、かつての中国と同様に世界に、そして日本に大きな影響を与える国は間違いなくインドでしょう。
インドは、かつての中国に似ている、という見方もできますが、次に述べる3点で、明らかに特異な国であるといえます。
それは、
ポイント1)発展途上国でありながら日本を超えるIT大国である
インドがかつての中国と大きく違うのは、発展途上国でありながら、日本を超えるようなIT大国である、という点です。
その理由はインドがアメリカの「グーグル」「アマゾン」「マイクロソフト」「メタ」といったビッグテックのソフトウェアの下請けを長年行っており、今や米国と同等以上のIT技術力を身に着けている、という点が最大の違いだということです。
ポイント2)世界最大の英語圏国家である
なぜアメリカのビッグテックがインドを下請けにしたのかというと、理由が大きく2つあります。
1つ目の理由は英語圏である、ということです。
これは非常に重要なポイントです。
インドはもともとイギリスの植民地であったこと(現在も英国連邦のメンバー国)、国内に多数の言語が存在することから、英語が準公用語になっており、インドの大学卒業者は英語を普通に話すことができます。
2つ目は時差の関係で、アメリカが夜の間、インドは昼間だということです。
つまり、アメリカで昼間の間に仕様を決めたプログラムをインドに発注します。
インドはアメリカが夜の間に開発を行い、アメリカが朝になった時には開発が終わったソースコードをアメリカに渡します。
アメリカのビッグテックは、こうしたサイクルを回すことで世界最強の開発力を実現しているのです。
ポイント3)世界最大の理系人材輩出国である
インドにはIIT(インド工科大学)という、アメリカのMIT(マサチューセッツ工科大学)に負けずとも劣らない国立工科大学が国内に23校あります。
またIIT以外にも数多くの理系大学がインドには存在しており、その毎年の理系人材の卒業生は150万人を超え、これは日本の理系人材の卒業生の10倍にあたります。
シリコンバレーのエコシステムがスタンフォード大学によって維持されている、といわれますが、インドも同様にIITを中心とした数多くの理系大学が、インドのITエコシステムの人材の供給源になっているのです。
そして船井総合研究所は、この2025年11月にインド・ベンガルールに現地法人「船井総研インディア」を設立します。
「船井総研インディア」の事業内容はGCC(グローバル・ケイパビリティ・センター)です。
インドに限らず、発展途上国に拠点をつくる、というと「オフショア」という言葉が先行します。
オフショアは人件費に代表されるあらゆるコストを下げることを目的としていますが、GCCというのはそうではなく、「R&D拠点」かつ「グローバル拠点」になることを目指しています。
拠点の目的が「オフショア」だと、つまり言い換えると「コストダウン」だけだと、コストが上昇するたびに、さらに人件費が安い国を探し回ることになります。
GCCも、結果的にコスト削減を目的にしています。
しかしコストダウンだけでなく、前述の「R&D拠点」「グローバル拠点」を目指している点が、大きな違いなのです。
実際、私たち自身が、現地法人立上げに伴い、現地でエンジニア採用を行いました。
日本国内だと、本当に優秀なエンジニアというのは面接を受けにきてくれるのがせいぜい月に1名いるかいないか。
年間で1~2名採用できるか、できないか、というレベルです。
ところがインドだと、わずか1ヶ月ほどの間に60名を超える優秀なエンジニアからの応募があり、その中から書類選考と複数回の面接を実施し、10名弱のエンジニアを、わずか2~3ヶ月ほどの間に採用することができました。
もちろん、コミュニケーションは英語で行う必要がありますが、これだけのリソースの採用は日本では到底不可能だと思います。
このように、かつての中国と同様に、「インドをいかに自社のビジネスに活用するべきなのか」というテーマが、非常に重要だと思います。
このテーマには、次の3つの切り口があると思います。
切り口1:インドのリソースを自社で活用する(=船井総研のパターン)
切り口2:インドを市場として捉える(=インドでの販路拡大)
切り口3:インドが将来、自社にどの様なライバルになるのか(=敵情視察?)
前述の「驚きのサステナグロースカンパニー視察セミナー in インド」ですが、お申込みの“早割適用期間”が、この11月末まで、となっておりますので早めのお申し込みをお奨めします。
繰り返しになりますが、今回のインド視察は、私 片山和也 も講師として参加いたします。
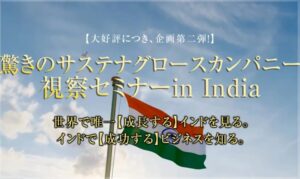
↓↓↓2026年2月開催「インド視察」の詳細・お申し込みは下記URLからどうぞ!
https://global.funaisoken.co.jp/in_session/in_session-india2026
ぜひ、皆様と本視察でご一緒できることを、心から楽しみにしております。
~主な視察先~
船井総研の視察でなければ絶対に視ることができない、必見の視察先の数々!
<視察先企業1:ZOHOインド本社(ゾーホー)>
徒歩では到底まわることができない広大な敷地の中に(電動カートに乗車しての視察になります)、ヨーロッパの都市を思わせる大理石のビルが次々に建設されており、その成長に圧倒されます。
ZOHO社が提供するCRMプラットフォームZohoは、世界150ヵ国以上で使用されており、全世界1億を超えるユーザーを抱える、世界有数のDXツールです。
今、特にZohoが注目されている理由はローコスト・中小中堅企業向け・全てのビジネスプロセスに対応していることに加えて、AI(生成AI)との親和性が極めて高いことです。
今回の視察では、中小中堅企業がいかにAI(生成AI)を自社に取り入れていくのか、をポイントに実践的な視察を行います。
<視察先企業2:アマゾン・楽天>
インドは今やコストダウン目的に進出する“オフショア”ではなく、R&D拠点・グローバル拠点として進出する”GCC(グローバル・ケイパビリティ・センター)”と、捉えられています。
実際、グローバルを代表するテック企業(EC企業)であるアマゾンは、インド・ベンガルールに世界最大級のGCCを設置しています。
また日本を代表するEC企業も、同様に大規模なGCCをベンガルールに設置しています。
今回は、この両者のGCCを視察することにより、世界を、そして日本を代表するテック企業がインドをいかに戦略的に活用しているのかを視察します。
<視察先企業3:Bhartiya City バルティア・シティ>
インドの大手都市デベロッパーであり、ベンガルール北部で住宅・商業・オフィス・教育・医療・スポーツ施設を一体化した複合都市の運用を行っています。
なお、同都市には三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)や、セブンイレブン・グローバルソリューションセンターも進出しています。
同都市は「都市の規模と村の温かさ」を併せ持つコミュニティとして、世界的にも注目を集めています。
<視察先企業4:NAVIS HR>
2002年にインド・ベンガルールで設立された、日本への人材送り出し機関です。
日本語の研修はもちろん、看護師・介護士・ホスピタリティ専門職やドライバーを対象として、専門教育を施した上で日本への即戦力人材の送り出しを行っています。
人手不足が深刻になる日本において、こうしたインド人材活用のポイントを探ります。
<視察先企業5:Meesho 他 インドのAI・DXスタートアップ企業>
Meeshoは、インド・ベンガルールから世界を変える革新的なネット通販企業として注目を集めています。
アマゾンなどの業界大手に対抗する新勢力として知られ、AIを活用した独自の顧客サービスで勝負しています。
他にも世界的に注目されるインドのAI・DXスタートアップ、天才を輩出する学術機関として知られるIIT(インド工科大学)マドラス校、「アーユルヴェーダの村」として知られるAyurvedaGram(アーユルヴェーダグラム) 他 への訪問を予定しています。
~このような方におススメのセミナーです~
・これから確実に伸びるインド市場をこの目で見ておきたい経営者の方
・本当の意味でDXやAIを自社に取り入れたいと考えている経営者の方
・世界で最も成長している市場、インドから何らかの示唆を得たい経営者の方
・インドでビジネスチャンスを探したい経営者の方
・この先の時代の流れを自社の成長のチャンスにつなげたいと考えている経営者の方
【視察セミナー概要】
日程◆ 2026/2/7 (土)~2/13(金)<7日間>
定員◆先着50名様
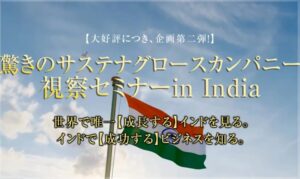
↓↓↓2026年2月開催「インド視察」の詳細・お申し込みは下記URLからどうぞ!
https://global.funaisoken.co.jp/in_session/in_session-india2026