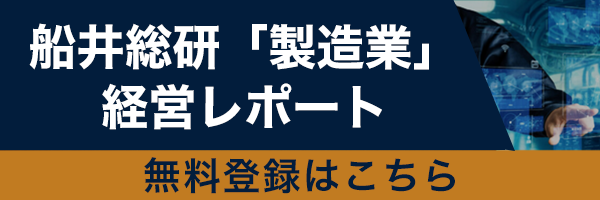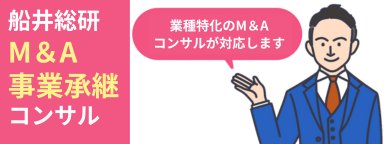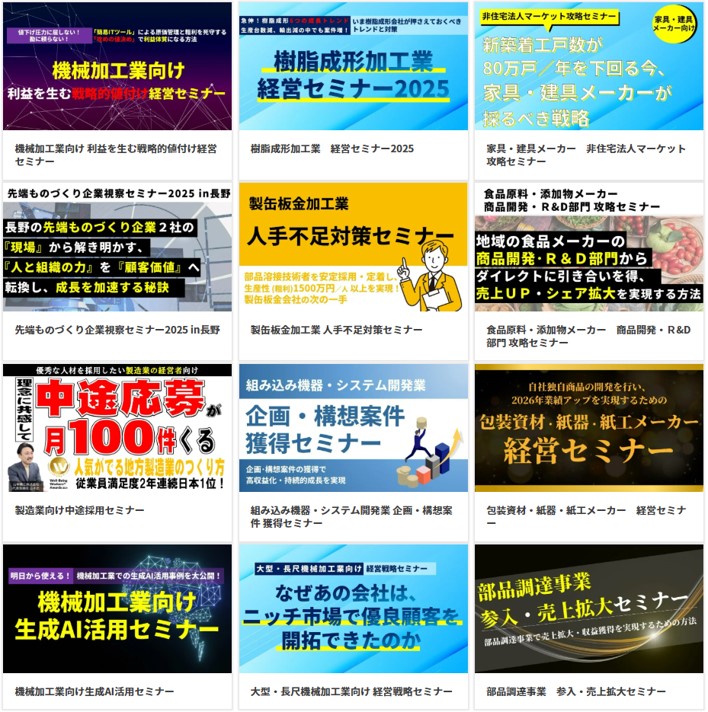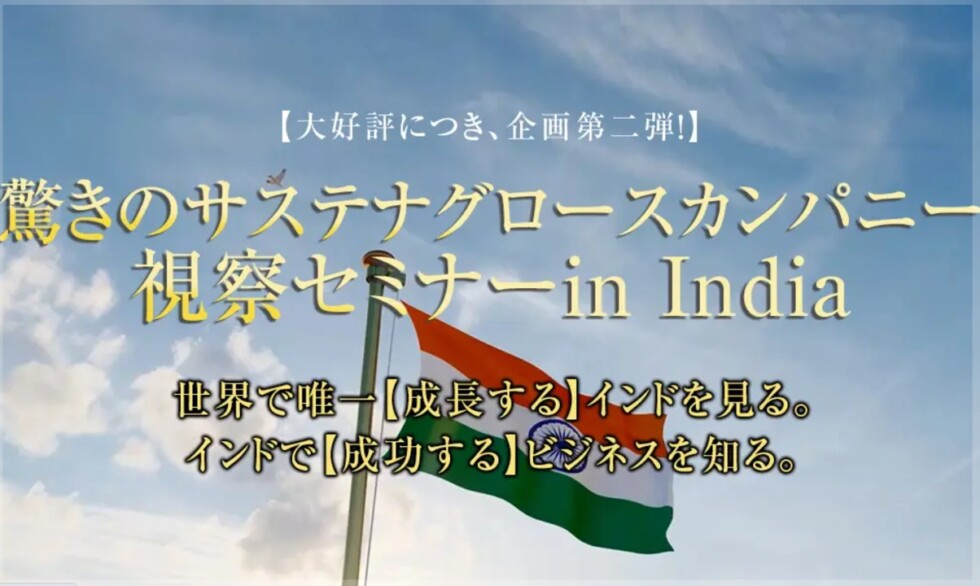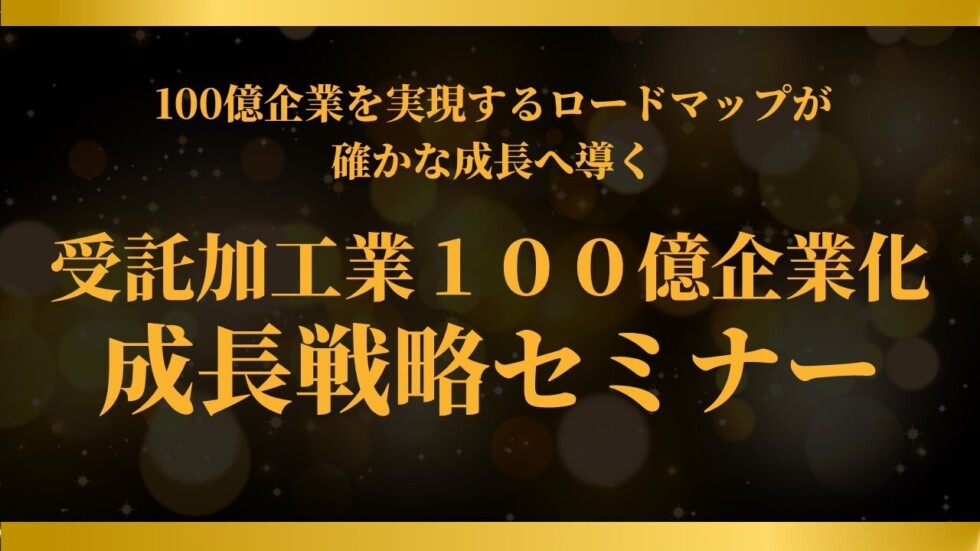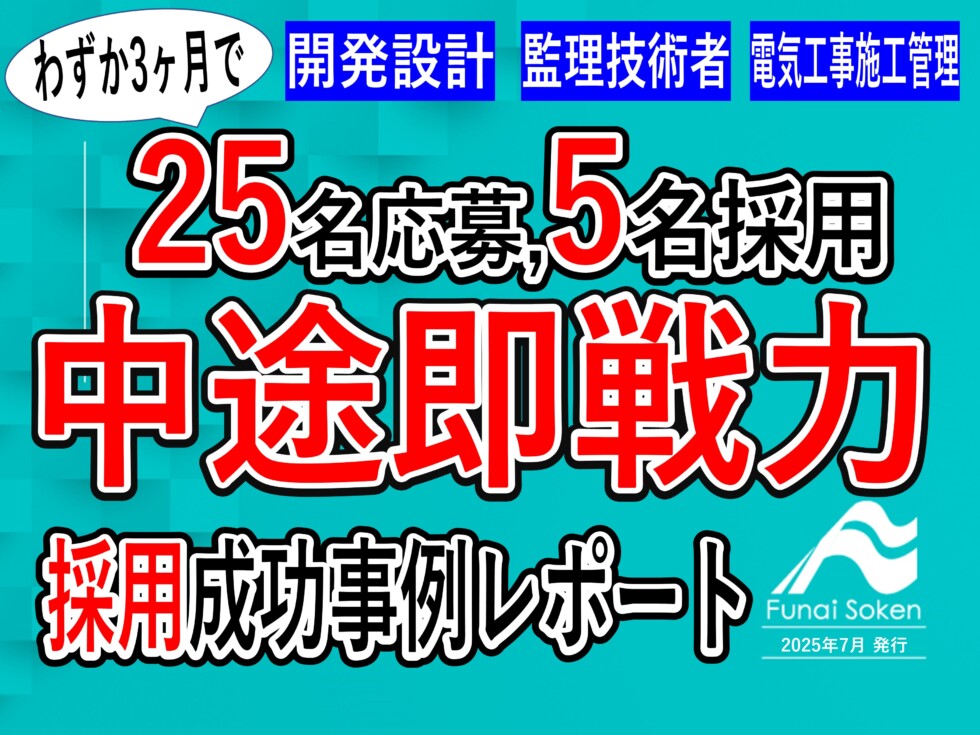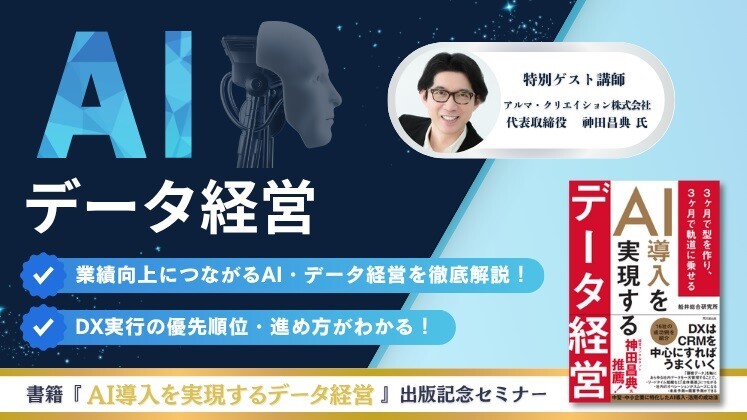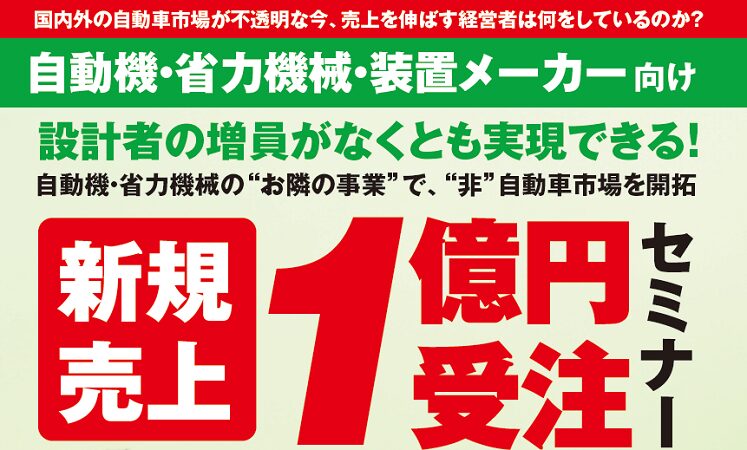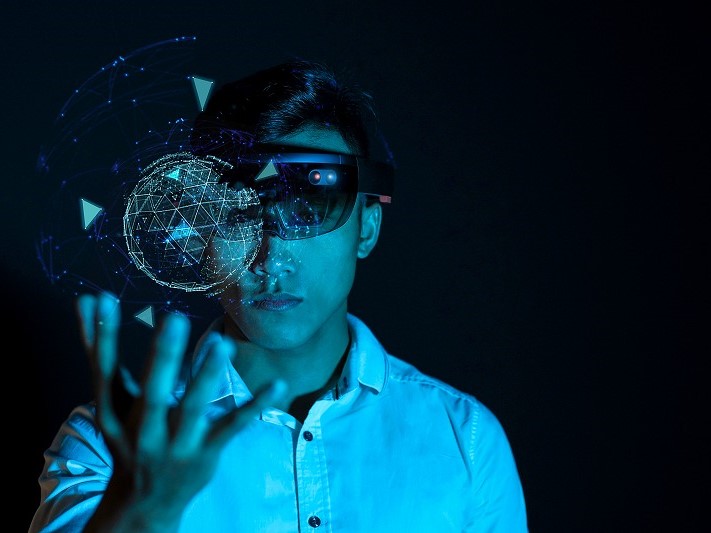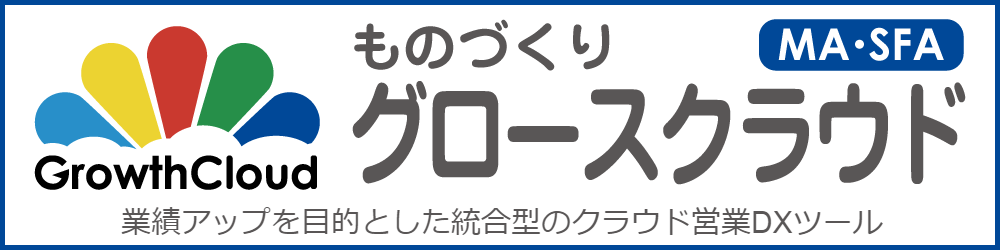なぜあの会社が倒産?京都の優良企業の倒産の衝撃
先般の新聞報道通り、この7月25日に京都のレーザー加工機・電池検査装置メーカーの片岡製作所(従業員210名)が、民事再生法を申請しました。
同社は電池検査装置や太陽電池の製造に使うレーザー加工機で高いシェアを持ち、成長市場の優良企業として知られていました。
京都市体育館のネーミングライツ(命名権)も取得、同体育館は「かたおかアリーナ京都」の名称となっていました。
また今年2月には国の補助金を活用して、京都市内に総工費68億円をかけて新工場を建設するとも報道されており、表面的には「なぜあの会社が倒産?」ともいえる、関係者を驚かせる倒産劇にみえます。
しかし関係筋の話では、2023~2024年の段階で某大手電機メーカー向けの20億円を超える設備の納入の目途がたたなくなり、2024年1月以降は事実上の不良在庫になっていたといいます。
さらに同年11月に、主要得意先であったスウェーデンの新興電池メーカー、ノースボルト社が破綻したことで大口の焦げ付きが発生。
資金難に陥って今回の民事再生法の申請に至ったといいます。
同社は、同社でなければできない特殊な加工技術を武器に業績を伸ばしてきた、いわば設備メーカーのモデル企業の様な存在でした。
ところがあっけなく、今回の倒産に至ったわけです。
外からだけではわからない、設備メーカー(セットメーカー)の経営リスク
設備メーカーの場合、外からみているだけではわからない経営リスクがあります。
例えば「発注書」をもらう前に、想定される納期に間に合わせるため、見切り発車で製造に着手してしまうケースは多々あります。
この状態で事実上のキャンセルになると、どうしようもありません。
また海外企業からの回収は、国内企業以上に困難です。
キャンセルになってしまった場合、あるいは今回のケースのように破綻してしまった場合、その法的な対応は中小企業の手に余ります。
今回の件の報道をみると「EV市場の環境の悪化」という表現が目立ちますが、そもそも経営的に構造的な要因(リスク)があったのかもしれません。
EV市場だけではない!常に先行き不透明・不安定な「エネルギー」関連ビジネス
そもそも、EVに限らず「エネルギー関係」のビジネスは、利権が大きいこともあってか市況は常に不安定です。
例えば2000年前半、米国のオバマ政権ではグリーン・ニューディール計画による空前の原子力発電所ブームが起きました。
おりからの原油高やCO2排出など温暖化への意識の高まりから、全米で100基を超える原子力発電所が計画されました。
当時は原子力ルネッサンスといわれ、例えば原子力発電所の圧力容器を手掛ける日本製鋼などは100年間の仕事が保障される、といわれるほど引合いが積みあがりました。
ところが2011年の東日本大震災で、原発ブームは一気に吹き飛びます。
原発関連企業の業績は低迷し、日本製鋼もこれが原因で、その後、数期は赤字が続いたと記憶しています。
その後は風力発電や太陽光発電など、いわゆる再生エネルギーが注目を浴びます。
ところが風力も太陽光もし烈な価格競争となり、風力発電は欧州企業に、太陽光発電は中国企業に主導権を奪われます。
そうこうするうちに生成AIブームが起き、結局、再生可能エネルギーでは安定的な電力供給が困難と、現在ではLNGや、再び原子力発電(小型原子力:SMR)に回帰しています。
一時期ブームだった水素も、結局のところコストが思った様に下がらず、現在ではほとんど聞かなくなってしまいました。
このようにEVに限らず、「エネルギー関係」のビジネスというのは浮沈が大きいのです。
中堅・中小企業(製造業・商社/販売店)の経営の鉄則
やはり今回のケースからの教訓は、特に中堅・中小企業においては「特定業界・特定顧客」に依存しない、ということです。
一見、取引先が多いようでも、同一業界への依存が売上全体の30%を超えているとしたら、それは経営的に改善が必要だと思います。
例えば製造業の領域だと、圧倒的にボリュームが大きいのは“自動車”マーケットです。
ボリュームが大きい分、どこの国でも経済インパクトが大きくなっている結果、今回のトランプ関税の渦中にいるのも自動車産業です。
また前述の通り、EV市場の先行きも新興国との競争も含めて不透明であると言わざるをえません。
「特定業界・特定顧客」依存からの脱却を図ろうとすると、まず求められるのは“営業力”です。
しかし慢性的な人手不足である昨今、優秀な営業担当者を雇用するのは至難の業。
ましてや、受託型製造業の場合は、ただ仕事を取ってくれば良いわけではなく、本当の意味で“自社の強みに適合した”仕事を取ってこなければ現場は動いてくれませんし、儲かりません。
そこで有効となるのが、従来型のこちらから売り込む「PUSH型営業」ではなく、顧客の方から問合せが来る「PULL型営業」を主体とする、営業DXです。
船井総合研究所では、中小製造業から商社(販売店)まで、数多くの営業DX導入実績があり、成功事例も多数あります。
<下記URLから、成功事例の動画33種類をご覧いただけます>
⇩YouTubeはこちらから⇩
https://www.youtube.com/@zohoyoutube1828/videos
また下記のように、オンラインセミナーも含め、数多くの業種に対して専門的な内容の経営セミナーを随時実施しています。
<船井総合研究所の中小製造業・商社/販売店向け経営セミナー(現在開催中)>
⇩開催中のセミナーはこちらから⇩
https://seizougyou-koujoukeiei.funaisoken.co.jp/seminar/
特に、上記の成功事例の動画はYoutube上にアップされた無料の動画になっています。
ぜひご覧いただき、自社の経営の参考にしていただければと思います。
製造業・工場経営の最新ノウハウ資料を見る